гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒҜгҖҒгӮҝгӮӨгғ—еҲҘпјҲгӮ·гғӘгӮігғі/гӮ·гғӘгӮігғій…ёеҢ–зү©гғ–гғ¬гғігғүгҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ гғҒгӮҝгғій…ёеҢ–зү©гҖҒгӮ·гғӘгӮігғігӮ«гғјгғңгғіиӨҮеҗҲжқҗгҖҒгӮ·гғӘгӮігғігӮ°гғ©гғ•гӮ§гғіиӨҮеҗҲжқҗгҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ йҮ‘еұһгҖҒгҒқгҒ®д»–пјүгҖҒгӮЁгғігғүгғҰгғјгӮ¶гғјеҲҘпјҲијёйҖҒгҖҒйӣ»ж°—гҒҠгӮҲгҒійӣ»еӯҗгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгҖҒгҒқгҒ®д»–пјүгҖҒеӣҪеҲҘгҖҒ競дәүгҖҒдәҲжё¬гҒҠгӮҲгҒіж©ҹдјҡгҖҒ2019-2029FгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request Customization| дәҲжё¬жңҹй–“ | 2025-2029 |
| еёӮе ҙиҰҸжЁЎпјҲ2023е№ҙпјү | 2е„„3,619дёҮзұігғүгғ« |
| еёӮе ҙиҰҸжЁЎпјҲ2029е№ҙпјү | 3е„„9,693дёҮзұігғүгғ« |
| CAGRпјҲ2024-2029е№ҙпјү | 9.21% |
| жңҖгӮӮжҖҘжҲҗй•·гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮ»гӮ°гғЎгғігғҲ | ијёйҖҒ |
| жңҖеӨ§еёӮе ҙ | дёӯеӣҪ |

еёӮе ҙжҰӮиҰҒ
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒҜгҖҒ2023е№ҙгҒ«2е„„3,619дёҮзұігғүгғ«гҒЁи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҖҒдәҲжё¬жңҹй–“дёӯгҒ«9.21пј…гҒ®CAGRгҒ§жҲҗй•·гҒ—гҖҒ2029е№ҙгҒ«гҒҜ3е„„9,693дёҮзұігғүгғ«гҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒҜгҖҒзү№гҒ«йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠпјҲEVпјүгҖҒж°‘з”ҹз”Ёйӣ»еӯҗж©ҹеҷЁгҖҒеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢй«ҳжҖ§иғҪгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒ®йңҖиҰҒеў—еҠ гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ§е№…гҒӘжҲҗй•·гҒҢиҰӢиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒҜгғҗгғғгғҶгғӘгғјиЈҪйҖ гҒ®дёӯеҝғең°гҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдёӯеӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒйҹ“еӣҪгҒӘгҒ©гҒ®еӣҪгҒҜгҖҒгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ йҮ‘еұһгҖҒеӣәдҪ“жқҗж–ҷгҒӘгҒ©гҒ®й«ҳеәҰгҒӘгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®й–ӢзҷәгҒЁжҺЎз”ЁгӮ’гғӘгғјгғүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж¬Ўдё–д»Јжқҗж–ҷгҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гӮ°гғ©гғ•гӮЎгӮӨгғҲгӮўгғҺгғјгғүгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒе„ӘгӮҢгҒҹгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҖҒгӮҲгӮҠйҖҹгҒ„е……йӣ»жҷӮй–“гҖҒгӮҲгӮҠй•·гҒ„гғҗгғғгғҶгғӘгғјеҜҝе‘ҪгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҖҒе°ҶжқҘгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өжҠҖиЎ“гҒ®йҮҚиҰҒгҒӘгӮігғігғқгғјгғҚгғігғҲгҒЁгҒ—гҒҰдҪҚзҪ®д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зӮӯзҙ жҺ’еҮәйҮҸгҒ®еүҠжёӣгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹж”ҝеәңгҒ®ж”ҝзӯ–гҒЁгӮӨгғігӮ»гғігғҶгӮЈгғ–гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®йңҖиҰҒгҒҢгҒ•гӮүгҒ«й«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜзү№гҒ«иҮӘеӢ•и»ҠйғЁй–ҖгҒ§йЎ•и‘—гҒ§гҖҒз’°еўғиҰҸеҲ¶гҒЁж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®йңҖиҰҒгҒ«еҝңгҒҲгҒҰйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒ®з”ҹз”ЈгҒҢеҠ йҖҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒ®еӨ§жүӢгғҗгғғгғҶгғӘгғјгғЎгғјгӮ«гғјгҒЁжқҗж–ҷдјҡзӨҫгҒ«гӮҲгӮӢз ”з©¶й–ӢзҷәгҒёгҒ®жҠ•иіҮгҒ®еў—еҠ гҒҜгҖҒгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷжҠҖиЎ“гҒ®йқ©ж–°гӮ’дҝғйҖІгҒ—гҖҒеҠ№зҺҮгҖҒгӮігӮ№гғҲеүҠжёӣгҖҒгӮ№гӮұгғјгғ©гғ“гғӘгғҶгӮЈгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҺҹжқҗж–ҷгҒ®гӮөгғ—гғ©гӮӨгғҒгӮ§гғјгғігҒ®еҲ¶зҙ„гҖҒиЈҪйҖ гҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гҖҒй«ҳгҒ„з”ҹз”ЈгӮігӮ№гғҲгҒӘгҒ©гҒ®иӘІйЎҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®жң¬ж јзҡ„гҒӘе•ҶжҘӯеҢ–гҒҢйҒ…гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғҠгғҺгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгҒЁжқҗж–ҷ科еӯҰгҒ®з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘй–ӢзҷәгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®е•ҸйЎҢгҒҢз·©е’ҢгҒ•гӮҢгҖҒй•·жңҹзҡ„гҒӘжҲҗй•·гҒҢдҝқиЁјгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁжңҹеҫ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дё»иҰҒгҒӘеёӮе ҙжҺЁйҖІиҰҒеӣ
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ§гҒ®йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒ®жҺЎз”ЁгҒ®еў—еҠ
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ§гҒ®йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»Ҡ (EV) гҒ®жҺЎз”ЁгҒ®еў—еҠ гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ®дё»иҰҒгҒӘжҺЁйҖІиҰҒеӣ гҒ§гҒҷгҖӮзӮӯзҙ жҺ’еҮәйҮҸгӮ’еүҠжёӣгҒ—гҖҒж°—еҖҷеӨүеӢ•гҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒжҖ§гҒҢе·®гҒ—иҝ«гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдёӯеӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒйҹ“еӣҪгҖҒгӮӨгғігғүгҒӘгҒ©гҒ®дё»иҰҒеёӮе ҙгҒ®ж”ҝеәңгҒҜгҖҒеҺіж јгҒӘж”ҝзӯ–гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒёгҒ®з§»иЎҢгӮ’еҠ йҖҹгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йӯ…еҠӣзҡ„гҒӘгӮӨгғігӮ»гғігғҶгӮЈгғ–гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҜҫзӯ–гҒ«гҒҜгҖҒEVиіје…ҘгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиЈңеҠ©йҮ‘гҖҒзЁҺгҒ®йӮ„д»ҳгҖҒEVе……йӣ»гӮӨгғігғ•гғ©гҒ®й–ӢзҷәгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒ®з”ҹз”ЈгҒЁиІ©еЈІгҒҢжҖҘеў—гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒ2060е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«гӮ«гғјгғңгғігғӢгғҘгғјгғҲгғ©гғ«гӮ’йҒ”жҲҗгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶз©ҚжҘөзҡ„гҒӘзӣ®жЁҷгӮ’жҺІгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢдё–з•ҢжңҖеӨ§гҒ®EVеёӮе ҙгҒ§гҒӮгӮӢдёӯеӣҪгҒ§гҒҜйЎ•и‘—гҒ§гҒҷгҖӮ
еҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјжәҗгҒӢгӮүгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өйңҖиҰҒгҒ®еў—еҠ
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ§гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®йңҖиҰҒгҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдё»гҒӘзҗҶз”ұгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪе…үгӮ„йўЁеҠӣгҒӘгҒ©гҒ®еҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјжәҗгҒёгҒ®дҫқеӯҳеәҰгҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮж”ҝеәңгӮ„з”ЈжҘӯз•ҢгҒҢжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪжҖ§гҒ®зӣ®жЁҷгӮ’йҒ”жҲҗгҒ—гҖҒзӮӯзҙ жҺ’еҮәйҮҸгӮ’еүҠжёӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮӨгғігғ•гғ©гҒ«еӨҡйЎҚгҒ®жҠ•иіҮгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігҒҜгҖҒж–ӯз¶ҡзҡ„гҒӘгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјжәҗгҒӢгӮүз”ҹжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢйӣ»еҠӣгҒ®дҝЎй јжҖ§гҒЁе®үе®ҡжҖ§гӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮйүӣи“„йӣ»жұ гҒӘгҒ©гҒ®еҫ“жқҘгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өжҠҖиЎ“гҒҜгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ«дјҙгҒҶй«ҳгҒ„гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјйңҖиҰҒгҒЁй•·жңҹиІҜи”өгҒ®гғӢгғјгӮәгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгӮӮгҒҜгӮ„дёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®дёҚи¶ігҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж¬Ўдё–д»ЈгҒ®гӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®й–ӢзҷәгҒЁе°Һе…ҘгҒҢеҠ йҖҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ гӮӨгӮӘгғійӣ»жұ гҒ®ж©ҹиғҪгҒҢеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҖҒеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгҒ®е®ҹзҸҫеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёӯеӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒйҹ“еӣҪгҒӘгҒ©гҒ®еӣҪгҖ…гҒҜгҖҒеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ«йҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒҚгҖҒй«ҳеәҰгҒӘиІҜи”өжҠҖиЎ“гӮ’зөұеҗҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғји»ўжҸӣгӮ’гғӘгғјгғүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«дёӯеӣҪгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪе…үгҒЁйўЁеҠӣгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ®й–ӢзҷәгҒ«йҮҺеҝғзҡ„гҒӘзӣ®жЁҷгӮ’жҺІгҒ’гҖҒеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ®жҺЎз”ЁгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдё–з•Ңзҡ„гғӘгғјгғҖгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҗҢеӣҪгҒ®е·ЁеӨ§гҒӘгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өеёӮе ҙгҒҜгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’еҠ№зҺҮзҡ„гҒ«иІҜи”өгҒҠгӮҲгҒіеҲҶй…ҚгҒ§гҒҚгӮӢй«ҳжҖ§иғҪгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒ®йңҖиҰҒгӮ’дҝғйҖІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒ®гӮўгғҺгғјгғүгҖҒеӣәдҪ“жқҗж–ҷгҖҒгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®д»–гҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжҠҖиЎ“гҒҢгғӘгғҒгӮҰгғ гӮӨгӮӘгғійӣ»жұ гҒ«зө„гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҒ®еҗ‘дёҠгҖҒеҜҝе‘ҪгҒ®е»¶й•·гҖҒе……йӣ»жҷӮй–“гҒ®зҹӯзё®гҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжӢЎејөжҖ§гҒЁй•·еҜҝе‘ҪгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ§гҒ®дҪҝз”ЁгҒ«жңҖйҒ©гҒ§гҒҷгҖӮеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒҢгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгғҹгғғгӮҜгӮ№гҒ§гӮ·гӮ§гӮўгӮ’жӢЎеӨ§гҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өжҠҖиЎ“гҒҜгҖҒгӮ°гғӘгғғгғүгҒ®е®үе®ҡжҖ§гӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјдҫӣзөҰгҒ®еӨүеӢ•гӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢдёҠгҒ§жҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®жҺЎз”ЁгҒ«ж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҹй«ҳеәҰгҒӘгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігҒ®йңҖиҰҒгҒҜгҖҒеӨ§е№…гҒ«еў—еҠ гҒҷгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еӮҫеҗ‘гҒҜгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ®жҲҗй•·гӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒең°еҹҹгҒ®гӮҲгӮҠеәғзҜ„гҒӘжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪжҖ§гҒЁгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиҮӘз«ӢгҒ®зӣ®жЁҷгҒ«гӮӮиІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
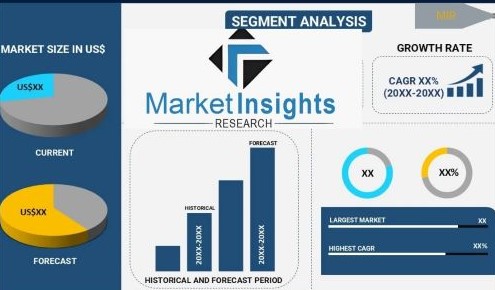
жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢж¶ҲиІ»иҖ…еҗ‘гҒ‘йӣ»еӯҗж©ҹеҷЁеёӮе ҙ
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ§жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢж¶ҲиІ»иҖ…еҗ‘гҒ‘йӣ»еӯҗж©ҹеҷЁеёӮе ҙгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ®жҲҗй•·гҒ®дё»гҒӘеҺҹеӢ•еҠӣгҒ§гҒҷгҖӮдё–з•ҢгҒ®йӣ»еӯҗж©ҹеҷЁз”ҹз”ЈгҒ®дёӯеҝғең°гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒ®ең°еҹҹгҒ«гҒҜгҖҒгӮ№гғһгғјгғҲгғ•гӮ©гғігҖҒгғ©гғғгғ—гғҲгғғгғ—гҖҒгӮҝгғ–гғ¬гғғгғҲгҖҒгӮҰгӮ§гӮўгғ©гғ–гғ«гғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒ®дё–з•Ңжңүж•°гҒ®гғЎгғјгӮ«гғјгҒҢжӢ зӮ№гӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёӯеӣҪгҖҒйҹ“еӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҒӘгҒ©гҒ®еӣҪгҒҢе…Ҳй ӯгҒ«з«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒҜгҒҫгҒҷгҒҫгҒҷй«ҳеәҰеҢ–гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гҒҜгӮҲгӮҠй«ҳйҖҹгҒ§й•·жҢҒгҒЎгҒ—гҖҒгӮҲгӮҠеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘгғҗгғғгғҶгғӘгғјжҖ§иғҪгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғӘгғҒгӮҰгғ гӮӨгӮӘгғійӣ»жұ гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҫ“жқҘгҒ®гӮ°гғ©гғ•гӮЎгӮӨгғҲгӮўгғҺгғјгғүгҒ®йҷҗз•ҢгҒҜгҖҒзү№гҒ«зҸҫд»ЈгҒ®й«ҳжҖ§иғҪйӣ»еӯҗж©ҹеҷЁгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјйңҖиҰҒгӮ’жәҖгҒҹгҒҷдёҠгҒ§гҒҫгҒҷгҒҫгҒҷжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®иӘІйЎҢгҒ«еҜҫеҮҰгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒҜгҖҒгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҖҒе……йӣ»йҖҹеәҰгҖҒгҒҠгӮҲгҒіе…ЁдҪ“зҡ„гҒӘеҜҝе‘ҪгӮ’еӨ§е№…гҒ«ж”№е–„гҒҷгӮӢгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒҠгӮҲгҒігғӘгғҒгӮҰгғ йҮ‘еұһгӮўгғҺгғјгғүгҒӘгҒ©гҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ«зӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йӣ»еӯҗж©ҹеҷЁиЈҪйҖ гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе„ӘдҪҚжҖ§гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдёӯеӣҪгҖҒйҹ“еӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҒҜгҖҒгғҗгғғгғҶгғӘгғјжҠҖиЎ“гӮ’еј·еҢ–гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«з ”究й–Ӣзҷә (R&D) гҒ«еӨҡйЎҚгҒ®жҠ•иіҮгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮӨгғҺгғҷгғјгӮ·гғ§гғігҒҜгҖҒгғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒ®жҖ§иғҪгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒдё–з•ҢгҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…еҗ‘гҒ‘йӣ»еӯҗж©ҹеҷЁеёӮе ҙгҒ§з«¶дәүеҠӣгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гӮӮдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒ®гӮўгғҺгғјгғүгҒҜгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢиғҪеҠӣгҒ«гӮҲгӮҠжіЁзӣ®гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒе……йӣ»й–“гҒ®гғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒ®дҪҝз”ЁжҷӮй–“гҒҢй•·гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒгғҗгғғгғҶгғӘгғјеҜҝе‘ҪгҒҢ延гҒігҖҒгғҰгғјгӮ¶гғјгӮЁгӮҜгӮ№гғҡгғӘгӮЁгғігӮ№гҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгғ•гӮЈгғғгғҲгғҚгӮ№гғҲгғ©гғғгӮ«гғјгӮ„гӮ№гғһгғјгғҲгӮҰгӮ©гғғгғҒгҒӘгҒ©гҒ®гӮҰгӮ§гӮўгғ©гғ–гғ«гҒ§гғ•гғ¬гӮӯгӮ·гғ–гғ«гҒӘйӣ»еӯҗж©ҹеҷЁгҒ®еў—еҠ гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®йңҖиҰҒгҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒ«гҒҜгҖҒи»ҪйҮҸгҒ§гғ•гғ¬гӮӯгӮ·гғ–гғ«гҒ§гҖҒгӮҲгӮҠй »з№ҒгҒӘе……йӣ»гӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒ«иҖҗгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй«ҳеәҰгҒӘгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒҢдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ§гҒҜгҖҒ家йӣ»иЈҪе“ҒгҒҢйҖІеҢ–гӮ’з¶ҡгҒ‘гҖҒдәәж°—гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒй«ҳжҖ§иғҪгҒӘж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®йңҖиҰҒгҒҢжҖҘеў—гҒҷгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жҲҗй•·гҒҷгӮӢ家йӣ»иЈҪе“ҒеёӮе ҙгҒҜгҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒҢжңҖж–°гғҮгғҗгӮӨгӮ№гҒ®жҠҖиЎ“йҖІжӯ©гҒЁгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјйңҖиҰҒгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ®жӢЎеӨ§гӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢдёҠгҒ§жҘөгӮҒгҒҰйҮҚиҰҒгҒӘеҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
дё»иҰҒгҒӘеёӮе ҙиӘІйЎҢ
зҶҫзғҲгҒӘ競дәүгҒЁеёӮе ҙгҒ®зҙ°еҲҶеҢ–
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒҜгҖҒзҶҫзғҲгҒӘ競дәүгҒЁеёӮе ҙгҒ®зҙ°еҲҶеҢ–гӮ’зү№еҫҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒи¶іе ҙгӮ’зҜүгҒ“гҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгғЎгғјгӮ«гғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘиӘІйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—ўеӯҳгҒ®гғҗгғғгғҶгғӘгғјгғЎгғјгӮ«гғјгҒӢгӮүж–°иҲҲгҒ®гӮ№гӮҝгғјгғҲгӮўгғғгғ—дјҒжҘӯгҒҫгҒ§гҖҒж•°еӨҡгҒҸгҒ®гғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒҢгҖҒжҖҘйҖҹгҒ«йҖІеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒ®еҲҶйҮҺгҒ§еёӮе ҙгӮ·гӮ§гӮўгӮ’競гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з«¶дәүз’°еўғгҒҜгҖҒдҫЎж јз«¶дәүгҖҒеҲ©зӣҠзҺҮгҒ®дҪҺдёӢгҖҒдјҒжҘӯгҒёгҒ®з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘйқ©ж–°гҒёгҒ®гғ—гғ¬гғғгӮ·гғЈгғјгҒ®еў—еӨ§гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еёӮе ҙгҒҜзҙ°еҲҶеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒҢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘзЁ®йЎһгҒ®гӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒЁгӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ«жіЁеҠӣгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒ®гӮўгғҺгғјгғүгҒ«зү№еҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдјҒжҘӯгӮӮгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ йҮ‘еұһгӮ„иӨҮеҗҲжқҗж–ҷгҒ«жіЁеҠӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдјҒжҘӯгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж–ӯзүҮеҢ–гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘгӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігӮ’жұӮгӮҒгӮӢйЎ§е®ўгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰзҠ¶жіҒгҒҢиӨҮйӣ‘гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒҢиЈҪе“ҒгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«е·®еҲҘеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдјҒжҘӯгҒҜгҖҒеёӮе ҙгӮ·гӮ§гӮўгӮ’зҚІеҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжҖ§иғҪгҒЁдҫЎж јгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғ–гғ©гғігғҮгӮЈгғігӮ°гҒЁйЎ§е®ўй–ўдҝӮгҒ§гӮӮ競дәүгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®з«¶дәүгҒ®жҝҖгҒ—гҒ„з’°еўғгӮ’д№—гӮҠеҲҮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒҜгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ·гғғгғ—гӮ„гӮігғ©гғңгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгғӘгӮҪгғјгӮ№гҒЁе°Ӯй–ҖзҹҘиӯҳгӮ’гғ—гғјгғ«гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиЈңе®Ңзҡ„гҒӘеј·гҒҝгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдјҒжҘӯгҒҜз ”з©¶й–ӢзҷәгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’еј·еҢ–гҒ—гҖҒиЈҪйҖ иғҪеҠӣгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгҖҒж–°иЈҪе“ҒгҒ®еёӮе ҙжҠ•е…ҘгҒҫгҒ§гҒ®жҷӮй–“гӮ’зҹӯзё®гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгғӢгғғгғҒеёӮе ҙгӮ„зү№ж®ҠгҒӘгӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ«жіЁеҠӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдјҒжҘӯгҒҢеёӮе ҙгҒ§зӢ¬иҮӘгҒ®ең°дҪҚгӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҖҒеӨ§жүӢдјҒжҘӯгҒЁгҒ®зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘ競дәүгҒҢи»ҪжёӣгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮөгғ—гғ©гӮӨгғҒгӮ§гғјгғігҒ®ж··д№ұгҒЁеҺҹжқҗж–ҷиӘҝйҒ”
гӮөгғ—гғ©гӮӨгғҒгӮ§гғјгғігҒ®ж··д№ұгҒЁеҺҹжқҗж–ҷиӘҝйҒ”гҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢиӘІйЎҢгҒҜгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§гҒҚгҒӘйҡңе®ігҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе…ҲйҖІзҡ„гҒӘгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®з”ҹз”ЈгҒҜгҖҒгӮ·гғӘгӮігғігҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ гҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®йҮҚиҰҒгҒӘйүұзү©гҒӘгҒ©гҒ®зү№е®ҡгҒ®еҺҹжқҗж–ҷгҒ«дҫқеӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒдҫЎж јеӨүеӢ•гӮ„ең°ж”ҝеӯҰзҡ„з·ҠејөгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҺҹжқҗж–ҷгҒ®е…ҘжүӢеҸҜиғҪжҖ§гҒ®еӨүеӢ•гҒҜз”ҹз”ЈгӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гӮ„гӮігӮ№гғҲгҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰдёҚзўәе®ҹжҖ§гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®жқҗж–ҷгҒ®гӮ°гғӯгғјгғҗгғ« гӮөгғ—гғ©гӮӨ гғҒгӮ§гғјгғігҒҜиӨҮйӣ‘гҒ§гҖҒиҮӘ然зҒҪе®ігҖҒиІҝжҳ“еҲ¶йҷҗгҖҒж”ҝжғ…дёҚе®үгҒ«гӮҲгӮӢж··д№ұгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮ„гҒҷгҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒCOVID-19 гғ‘гғігғҮгғҹгғғгӮҜгҒҜгӮ°гғӯгғјгғҗгғ« гӮөгғ—гғ©гӮӨ гғҒгӮ§гғјгғігҒ®и„ҶејұжҖ§гӮ’жө®гҒҚеҪ«гӮҠгҒ«гҒ—гҖҒеҺҹжқҗж–ҷгҒ®й…ҚйҖҒгҒ®йҒ…гӮҢгӮ„гғЎгғјгӮ«гғјгҒ®гӮігӮ№гғҲеў—еҠ гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдјҒжҘӯгҒҢж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®йңҖиҰҒеў—еӨ§гҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«з”ҹз”ЈгӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢдёӯгҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮөгғ—гғ©гӮӨ гғҒгӮ§гғјгғігҒ®иӘІйЎҢгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгӮөгғ—гғ©гӮӨ гғҒгӮ§гғјгғігҒ®гғӘгӮ№гӮҜгӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒҜиӘҝйҒ”жҲҰз•ҘгҒ®еӨҡж§ҳеҢ–гҖҒиӨҮж•°гҒ®гӮөгғ—гғ©гӮӨгғӨгғјгҒЁгҒ®й–ўдҝӮж§ӢзҜүгҖҒзҸҫең°иӘҝйҒ”гӮӨгғӢгӮ·гӮўгғҒгғ–гҒёгҒ®жҠ•иіҮгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдјҒжҘӯгҒҜгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гӮ„еҫӘз’°еһӢзөҢжёҲгҒ®е®ҹи·өгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдҪҝз”ЁжёҲгҒҝгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒӢгӮүиІҙйҮҚгҒӘжқҗж–ҷгӮ’еӣһеҸҺгҒ—гҖҒж–°гҒҹгҒ«жҺЎжҺҳгҒ•гӮҢгҒҹиіҮжәҗгҒёгҒ®дҫқеӯҳгӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
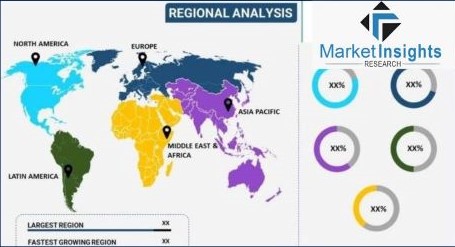
дё»иҰҒгҒӘеёӮе ҙеӢ•еҗ‘
еӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ®еҮәзҸҫ
еӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ®еҮәзҸҫгҒҜгҖҒгғҗгғғгғҶгғӘгғјжҠҖиЎ“гҒ®йқ©ж–°зҡ„гҒӘйҖІжӯ©гӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгӮ’еӨ§гҒҚгҒҸзүҪеј•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж¶ІдҪ“йӣ»и§ЈиіӘгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢеҫ“жқҘгҒ®гғӘгғҒгӮҰгғ гӮӨгӮӘгғійӣ»жұ гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒеӣәдҪ“йӣ»жұ гҒҜеӣәдҪ“йӣ»и§ЈиіӘгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҲ©зӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜгҖҒгӮҲгӮҠй«ҳгҒ„гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҖҒеј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹе®үе…Ёж©ҹиғҪгҖҒгӮҲгӮҠй•·гҒ„гӮөгӮӨгӮҜгғ«еҜҝе‘ҪгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒзү№гҒ«йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠпјҲEVпјүгӮ„ж°‘з”ҹз”Ёйӣ»еӯҗж©ҹеҷЁгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘз”ЁйҖ”гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ®жҖ§иғҪгҒЁеҠ№зҺҮгҒҜгҖҒдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ«еӨ§гҒҚгҒҸдҫқеӯҳгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ йҮ‘еұһгӮ„гӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒ®гӮўгғҺгғјгғүгҒӘгҒ©гҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ«еј·гҒ„й–ўеҝғгҒҢйӣҶгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жқҗж–ҷгҒҜгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өиғҪеҠӣгҒҢй«ҳгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®йқ©ж–°зҡ„гҒӘйӣ»жұ гӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгҒ«зү№гҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬гӮ„йҹ“еӣҪгҒӘгҒ©гҒ®еӣҪгҒҜгҖҒдё–з•ҢеёӮе ҙгҒ§з«¶дәүдёҠгҒ®е„ӘдҪҚжҖ§гӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҖҒеӨ§жүӢиҮӘеӢ•и»ҠгҒҠгӮҲгҒігӮЁгғ¬гӮҜгғҲгғӯгғӢгӮҜгӮ№дјҒжҘӯгҒӢгӮүгҒ®еӨҡйЎҚгҒ®жҠ•иіҮгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ®й–ӢзҷәгӮ’гғӘгғјгғүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒж—Ҙжң¬дјҒжҘӯгҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеӯҰиЎ“ж©ҹй–ўгӮ„ж–°иҲҲдјҒжҘӯгҒЁеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгҖҒгғҗгғғгғҶгғӘгғјжҖ§иғҪгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеӣәдҪ“жҠҖиЎ“гҒ®з ”究й–ӢзҷәгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ«й«ҳеәҰгҒӘгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе„ӘгӮҢгҒҹгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјжҖ§иғҪгҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҖҒе•ҶжҘӯз’°еўғгҒ§гҒ®гҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҠҖиЎ“гҒ®е®ҹзҸҫеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ®жҪңеңЁзҡ„гҒӘз”ЁйҖ”гҒҜгҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒж°‘з”ҹз”Ёйӣ»еӯҗж©ҹеҷЁгҖҒеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгҖҒгӮ°гғӘгғғгғүгӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ«гҒҫгҒ§еҸҠгҒігҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®йӣ»жұ гҒҢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҲҶйҮҺгҒ§гӮҲгӮҠе®ҹзҸҫеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒй«ҳжҖ§иғҪгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®йңҖиҰҒгҒҢжҖҘеў—гҒҷгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йңҖиҰҒгҒ®еў—еҠ гҒҜгҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒҢеӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ®зү№е®ҡгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢдёӯгҒ§гҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ®жҲҗй•·гӮ’зүҪеј•гҒҷгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеӣәдҪ“йӣ»жұ жҠҖиЎ“гҒҢжҲҗзҶҹгӮ’з¶ҡгҒ‘гҖҒиЈҪйҖ гҒ®гӮ№гӮұгғјгғ©гғ“гғӘгғҶгӮЈгӮ„жқҗж–ҷгҒ®йҒ©еҗҲжҖ§гҒӘгҒ©гҒ®зҸҫеңЁгҒ®иӘІйЎҢгӮ’е…ӢжңҚгҒҷгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒдәҲжғігҒ•гӮҢгӮӢеәғзҜ„гҒӘжҺЎз”ЁгҒҜгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®йқ©ж–°гӮ’и§ҰеӘ’гҒ—гҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®еёӮе ҙжҲҗй•·гӮ’гҒ•гӮүгҒ«жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
йӣ»жұ йқ©ж–°гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҲҰз•Ҙзҡ„гӮігғ©гғңгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒЁгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ·гғғгғ—
2024е№ҙ3жңҲгҖҒгғҚгғғгғҲгӮјгғӯжҺ’еҮәгҒёгҒ®з§»иЎҢгӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹиӢұеӣҪгӮ’жӢ зӮ№гҒЁгҒҷгӮӢгӮҜгғӘгғјгғігғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒӮгӮӢAltiliumгҒҜгҖҒйӣ»жұ жқҗж–ҷгҒЁжҠҖиЎ“гӮ’е°Ӯй–ҖгҒЁгҒҷгӮӢдјҒжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢTalga Group LtdгҒЁгҒ®е…Ҳй§Ҷзҡ„гҒӘгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ·гғғгғ—гӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮігғ©гғңгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒҜгҖҒе»ғжӯўгҒ•гӮҢгҒҹйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠпјҲEVпјүгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒӢгӮүгӮ°гғ©гғ•гӮЎгӮӨгғҲгӮ’еӣһеҸҺгҒ—гҖҒж–°гҒ—гҒ„гғҗгғғгғҶгғӘгғјгӮўгғҺгғјгғүгҒ®иЈҪйҖ гҒ«еҶҚеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҫӘз’°еһӢзөҢжёҲгӮ’дҝғйҖІгҒ—гҖҒиӢұеӣҪгҒ®ијёе…ҘеҺҹжқҗж–ҷгҒёгҒ®дҫқеӯҳгӮ’жёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®жҸҗжҗәгҒҜгҖҒиӢұеӣҪгҒ®EVгғҗгғғгғҶгғӘгғјйғЁй–Җеҗ‘гҒ‘гҒ®жҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘеӣҪеҶ…гӮ°гғ©гғ•гӮЎгӮӨгғҲдҫӣзөҰжәҗгӮ’зўәз«ӢгҒҷгӮӢдёҠгҒ§еӨ§гҒҚгҒӘеүҚйҖІгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҮӘеӢ•и»ҠгҒ®OEMпјҲзӣёжүӢе…Ҳгғ–гғ©гғігғүдҫӣзөҰпјүгҒЁгғҗгғғгғҶгғӘгғјгғЎгғјгӮ«гғјгҒ«дҪҺзӮӯзҙ гғҗгғғгғҶгғӘгғјжқҗж–ҷгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдёЎзӨҫгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’еј·иӘҝгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®жҸҗжҗәгҒ®иғҢеҫҢгҒ«гҒӮгӮӢдё»гҒӘеӢ•ж©ҹгҒ®1гҒӨгҒҜгҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠпјҲEVпјүгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…еҗ‘гҒ‘йӣ»еӯҗж©ҹеҷЁгҖҒеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ©гҒ®йңҖиҰҒгҒ®й«ҳгҒ„з”ЁйҖ”еҗ‘гҒ‘гҒ«гғҗгғғгғҶгғӘгғјжҖ§иғҪгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢеҝ…иҰҒжҖ§гҒ§гҒҷгҖӮеҫ“жқҘгҒ®гӮ°гғ©гғ•гӮЎгӮӨгғҲгӮўгғҺгғјгғүгҒҜгҖҒзҸҫд»ЈгҒ®гғҮгғҗгӮӨгӮ№гӮ„EVгҒ®й«ҳгҒҫгӮӢгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҖҒе……йӣ»йҖҹеәҰгҖҒеҜҝе‘ҪгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ«гҒҜдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®дјҒжҘӯгҖҒзү№гҒ«дёӯеӣҪгҖҒйҹ“еӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҒӘгҒ©гҒ®еӣҪгҒ§гҒҜгҖҒгӮҲгӮҠеҠ№зҺҮзҡ„гҒ§й«ҳжҖ§иғҪгҒӘгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгӮ’й–ӢзҷәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒдё–з•Ңзҡ„гҒӘгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјдјҒжҘӯгҒЁжҲҰз•Ҙзҡ„жҸҗжҗәгӮ’зөҗгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒҠгӮҲгҒігғӘгғҒгӮҰгғ йҮ‘еұһгӮўгғҺгғјгғүгҒҜгҖҒгӮҲгӮҠй«ҳгҒ„гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҒЁгӮҲгӮҠйҖҹгҒ„е……йӣ»ж©ҹиғҪгӮ’жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж¬Ўдё–д»ЈгғҗгғғгғҶгғӘгғјгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйӯ…еҠӣзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮеӯҰиЎ“ж©ҹй–ўгҒЁжҘӯз•ҢгғӘгғјгғҖгғјгҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ·гғғгғ—гҒҜгҖҒжқҗж–ҷ科еӯҰгҒ®йЈӣиәҚзҡ„йҖІжӯ©гӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®гӮігғ©гғңгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒҜгҖҒгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒ®гӮўгғҺгғјгғүгҒ®дҪ“з©ҚиҶЁејөгҒ®з·©е’ҢгӮ„еӣәдҪ“йӣ»жұ гҒ®иЈҪйҖ гҒ®иӨҮйӣ‘гҒ•гҒёгҒ®еҜҫеҮҰгҒӘгҒ©гҖҒж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢдё»иҰҒгҒӘиӘІйЎҢгҒ®е…ӢжңҚгҒ«йҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ»гӮ°гғЎгғігғҲеҲҘгӮӨгғігӮөгӮӨгғҲ
гӮҝгӮӨгғ—
гӮҝгӮӨгғ—еҲҘгҒ§гҒҜгҖҒгӮ·гғӘгӮігғі/гӮ·гғӘгӮігғій…ёеҢ–зү©гғ–гғ¬гғігғүгҒҢгҖҒгҒқгҒ®е„ӘгӮҢгҒҹжҖ§иғҪзү№жҖ§гҒЁгҖҒзү№гҒ«йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»Ҡ (EV) гӮ„家йӣ»иЈҪе“ҒгҒӘгҒ©гҒ®гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘз”ЁйҖ”гҒ§гҒ®йңҖиҰҒеў—еҠ гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзҸҫеңЁгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ§дё»жөҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒ®гӮўгғҺгғјгғүгҒҜгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гӮ°гғ©гғ•гӮЎгӮӨгғҲгӮўгғҺгғјгғүгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҒҢеӨ§е№…гҒ«й«ҳгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒҜгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’иІҜи”өгҒ—гҖҒеӢ•дҪңеҜҝе‘ҪгӮ’延гҒ°гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®зү№жҖ§гҒҜгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘз”ЁйҖ”гҒ§гҒ®йӣ»еҠӣйңҖиҰҒгҒ®й«ҳгҒҫгӮҠгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжҘӯз•ҢгҒҢгӮҲгӮҠеҠ№зҺҮзҡ„гҒӘгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігҒёгҒЁз§»иЎҢгҒҷгӮӢдёӯгҒ§зү№гҒ«йҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮўгғҺгғјгғүж§ӢйҖ гҒ«гӮ·гғӘгӮігғій…ёеҢ–зү©гӮ’зө„гҒҝиҫјгӮҖгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжқҗж–ҷгҒ®ж©ҹжў°зҡ„е®үе®ҡжҖ§гҒҢеҗ‘дёҠгҒ—гҖҒзҙ”зІӢгҒӘгӮ·гғӘгӮігғігҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘиӘІйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢе……ж”ҫйӣ»гӮөгӮӨгӮҜгғ«дёӯгҒ®дҪ“з©ҚиҶЁејөгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’еҠ№жһңзҡ„гҒ«з·©е’ҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж”№иүҜгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮўгғҺгғјгғүгҒ®иҖҗд№…жҖ§гҒҢеҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ гӮӨгӮӘгғійӣ»жұ гҒ®е…ЁдҪ“зҡ„гҒӘжҖ§иғҪгӮӮжңҖйҒ©еҢ–гҒ•гӮҢгҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒЁж¶ҲиІ»иҖ…гҒ®дёЎж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮҲгӮҠйӯ…еҠӣзҡ„гҒӘйҒёжҠһиӮўгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғје®№йҮҸгҒ®еў—еҠ гҖҒгӮөгӮӨгӮҜгғ«е®үе®ҡжҖ§гҒ®еҗ‘дёҠгҖҒгӮ·гғӘгӮігғі/гӮ·гғӘгӮігғій…ёеҢ–зү©гғ–гғ¬гғігғүгҒ®еҜҝе‘ҪгҒ®е»¶й•·гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҜгҖҒе•ҶжҘӯзҡ„е®ҹзҸҫеҸҜиғҪжҖ§гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸиІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгӮ·гғӘгӮігғігғҷгғјгӮ№гҒ®гӮўгғҺгғјгғүжҠҖиЎ“гҒ®з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘйҖІжӯ©гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ§гҒ®гҒ•гӮүгҒӘгӮӢжҺЎз”ЁгҒЁйқ©ж–°гҒҢдҝғйҖІгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮЁгғігғүгғҰгғјгӮ¶гғјгҒ®жҙһеҜҹ
гӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ§гҒҜгҖҒдё»гҒ«йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠпјҲEVпјүжҘӯз•ҢгҒ®и‘—гҒ—гҒ„жҲҗй•·гҒ«зүҪеј•гҒ•гӮҢгҖҒијёйҖҒйғЁй–ҖгҒҢдё»иҰҒгҒӘгӮЁгғігғүгғҰгғјгӮ¶гғјгҒЁгҒ—гҒҰйҡӣз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ ең°еҹҹе…ЁдҪ“гҒ®ж”ҝеәңгҒҜгҖҒж°—еҖҷеӨүеӢ•гӮ’з·©е’ҢгҒ—гҖҒзӮӯзҙ жҺ’еҮәйҮҸгӮ’еүҠжёӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжҲҰз•ҘгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘијёйҖҒгӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ“гҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒEVе°Ӯз”ЁгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹй«ҳжҖ§иғҪгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒ®йңҖиҰҒгҒҢеӨ§е№…гҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҜҶеәҰгҖҒе……йӣ»йҖҹеәҰгҖҒе…ЁдҪ“зҡ„гҒӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«еҜҝе‘ҪгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгғҗгғғгғҶгғӘгғјжҖ§иғҪжҢҮжЁҷгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢй«ҳеәҰгҒӘгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®й–ӢзҷәгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹжҠ•иіҮгҒҢи‘—гҒ—гҒҸеў—еҠ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёӯеӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒйҹ“еӣҪгҒӘгҒ©гҒ®еӣҪгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®з§»иЎҢгҒ®жңҖеүҚз·ҡгҒ«з«ӢгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒ®жҖҘйҖҹгҒӘе°Һе…ҘгӮ’зөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йңҖиҰҒгҒ®й«ҳгҒҫгӮҠгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮ·гғӘгӮігғі/гӮ·гғӘгӮігғій…ёеҢ–зү©гғ–гғ¬гғігғүгӮ„гӮ·гғӘгӮігғігӮ°гғ©гғ•гӮ§гғіиӨҮеҗҲжқҗж–ҷгҒӘгҒ©гҒ®йқ©ж–°зҡ„гҒӘж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®й«ҳеәҰгҒӘжқҗж–ҷгҒҜгҖҒиө°иЎҢи·қйӣўгҒ®е»¶й•·гҒЁе……йӣ»жҷӮй–“гҒ®еӨ§е№…гҒӘзҹӯзё®гӮ’е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгғҗгғғгғҶгғӘгғјгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҸҫд»ЈгҒ®йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒ®еҺігҒ—гҒ„жҖ§иғҪиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«дёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒијёйҖҒйғЁй–ҖгҒ®йӣ»еӢ•еҢ–гҒёгҒ®з„ҰзӮ№гҒҜгҖҒгғЎгғјгӮ«гғјгҒҢгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒ®еҠ№зҺҮгҒЁжҖ§иғҪгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢжқҗж–ҷгӮ’жҺўгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ®жҲҗй•·гӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒЁдәҲжғігҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
еӣҪеҲҘгӮӨгғігӮөгӮӨгғҲ
дёӯеӣҪгҒҜгҖҒгӮўгӮёгӮўеӨӘе№іжҙӢең°еҹҹгҒ®ж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷеёӮе ҙгҒ®ж”Ҝй…Қзҡ„гҒӘеӣҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еј·еҠӣгҒӘйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠпјҲEVпјүз”ЈжҘӯгҒЁгғҗгғғгғҶгғӘгғјжҠҖиЎ“гҒёгҒ®еӨҡйЎҚгҒ®жҠ•иіҮгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдё–з•ҢгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдёӯеӣҪж”ҝеәңгҒҜгҖҒEVгғЎгғјгӮ«гғјгҒЁж¶ҲиІ»иҖ…гҒёгҒ®иЈңеҠ©йҮ‘гӮ’еҗ«гӮҖгҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еәғзҜ„гҒӘж”ҝзӯ–гҒЁгӮӨгғӢгӮ·гӮўгғҒгғ–гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҒ®з”ҹз”ЈгҒЁиІ©еЈІгҒҢеүҚдҫӢгҒ®гҒӘгҒ„гҒ»гҒ©жҖҘеў—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®й«ҳжҖ§иғҪгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒ®йңҖиҰҒгҒҜгҖҒгӮ·гғӘгӮігғі/гӮ·гғӘгӮігғій…ёеҢ–зү©гғ–гғ¬гғігғүгӮ„гӮ·гғӘгӮігғігӮ°гғ©гғ•гӮ§гғіиӨҮеҗҲжқҗж–ҷгҒӘгҒ©гҒ®й«ҳеәҰгҒӘгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’дҝғйҖІгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дёӯеӣҪгҒ«гҒҜдё–з•ҢжңҖеӨ§гҒ®гғҗгғғгғҶгғӘгғјгғЎгғјгӮ«гғјгҒҢгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒӮгӮҠгҖҒгғҗгғғгғҶгғӘгғјгҒ®жҖ§иғҪгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢж¬Ўдё–д»ЈгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®з ”究й–ӢзҷәгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮӨгғҺгғҷгғјгӮ·гғ§гғігҒЁжӢЎејөжҖ§гҒ«йҮҚзӮ№гӮ’зҪ®гҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдёӯеӣҪгҒҜеёӮе ҙгҒ®жңҖеүҚз·ҡгҒ«з«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҺҹжқҗж–ҷгҒ®гӮөгғ—гғ©гӮӨгғҒгӮ§гғјгғігҒҢзўәз«ӢгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиЈҪйҖ иғҪеҠӣгӮӮй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒдё»е°Һзҡ„гҒӘең°дҪҚгҒҢгҒ•гӮүгҒ«еј·еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒЁгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјиІҜи”өгӮҪгғӘгғҘгғјгӮ·гғ§гғігҒёгҒ®дёӯеӣҪгҒ®жҠ•иіҮгҒҜзӣёд№—еҠ№жһңгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҖҒй«ҳеәҰгҒӘгғҗгғғгғҶгғӘгғјжҠҖиЎ“гҒ®йңҖиҰҒгӮ’й«ҳгӮҒгҖҒе„ӘгӮҢгҒҹгӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮ’гҒ•гӮүгҒ«й«ҳгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖиҝ‘гҒ®еӢ•еҗ‘
- 2023е№ҙ12жңҲгҖҒдёӯеӣҪгҒ®ShanshanгҒҜгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ§гҒ®гғҗгғғгғҶгғӘгғјйңҖиҰҒгҒ®еў—еҠ гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүгҒ«гӮўгғҺгғјгғүжқҗж–ҷиЈҪйҖ ж–ҪиЁӯгӮ’иЁӯз«ӢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«13е„„гғҰгғјгғӯпјҲ14е„„гғүгғ«пјүгӮ’жҠ•иіҮгҒҷгӮӢж„Ҹеҗ‘гӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҠжө·жқүжқүгғӘгғҒгӮҰгғ йӣ»жұ жқҗж–ҷ科жҠҖжңүйҷҗе…¬еҸёгҒҜгҖҒ12жңҲ15ж—Ҙд»ҳгғ—гғ¬гӮ№гғӘгғӘгғјгӮ№гҒ§гҖҒгғ•гӮЈгғігғ©гғігғүиҘҝжө·еІёгҒ®гӮ®гӮ¬гғҗгғјгӮөе·ҘжҘӯеӣЈең°еҶ…гҒ«еҗҢе·Ҙе ҙе»әиЁӯз”Ёең°гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҹгҒЁзҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖӮ
- 2023е№ҙ11жңҲгҖҒйӣ»жұ жқҗж–ҷгғ»жҠҖиЎ“гӮ’е°Ӯй–ҖгҒЁгҒҷгӮӢгӮҝгғ«гӮ¬гӮ°гғ«гғјгғ—ж ӘејҸдјҡзӨҫгҒҜгҖҒгӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғігҒ®йӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгғЎгғјгӮ«гғјгҖҒгғқгғјгғ«гӮ№гӮҝгғјгғ‘гғ•гӮ©гғјгғһгғігӮ№ABпјҲд»ҘдёӢгҖҢгғқгғјгғ«гӮ№гӮҝгғјгҖҚпјүгҒЁгҖҒгғқгғјгғ«гӮ№гӮҝгғј0гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲеҗ‘гҒ‘иІ жҘөжқҗж–ҷгҒ®й–ӢзҷәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжӢҳжқҹеҠӣгҒ®гҒӮгӮӢз ”з©¶еҘ‘зҙ„пјҲд»ҘдёӢгҖҢеҘ‘зҙ„гҖҚпјүгӮ’з· зөҗгҒ—гҒҹгҒЁзҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖӮгғқгғјгғ«гӮ№гӮҝгғј0гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҜгҖҒ2030е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«ж°—еҖҷдёӯз«ӢгҒ®йҮҸз”Ји»ҠгӮ’й–ӢзҷәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢпјҲд»ҘдёӢгҖҢгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҚпјүгҖӮ
- 2023е№ҙ11жңҲгҖҒгҖҢеӨ©ж–үгҒ®жүҚиғҪгҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ гҒ§дё–з•ҢгӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҖҚгҒЁйЎҢгҒ—гҒҹ第2еӣһеӨ©ж–үгғӘгғҒгӮҰгғ гӮӨгғҺгғҷгғјгӮ·гғ§гғігӮ·гғјгӮәгғігҒҢжҲҗеҠҹиЈҸгҒ«зөӮдәҶгҒ—гҒҹгҖӮ гҖҢеӣҪйҡӣгғ–гғ©гғігғүгҖҒгӮӘгғјгғ—гғігғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҖҒгғ—гғӯгғ•гӮ§гғғгӮ·гғ§гғҠгғ«гҒӘ競дәүгҖҚгӮ’гғҶгғјгғһгҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒ®гӮӨгғҷгғігғҲгҒ§гҒҜгҖҒ第2еӣһеӨ©ж–үгғӘгғҒгӮҰгғ иө·жҘӯгӮігғігғҶгӮ№гғҲгҖҒгғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгӮЁгӮігғӯгӮёгғјгӮ«гғігғ•гӮЎгғ¬гғігӮ№гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘеҶҶеҚ“иЁҺи«–дјҡгҒӘгҒ©гҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®дё»иҰҒгҒӘиҰҒзҙ гҒҢеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮӨгғӢгӮ·гӮўгғҒгғ–гҒҜгҖҒгғӘгғҒгӮҰгғ жҘӯз•ҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒ§йқ©ж–°зҡ„гҒӘжҲҗй•·гӮ’дҝғйҖІгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒе„ӘгӮҢгҒҹиө·жҘӯгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ®иӮІжҲҗгҒЁе®ҹиЎҢгӮ’еӨ§е№…гҒ«еј·еҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖиҝ‘гҒ®й–Ӣзҷә
- еҜ§жіўжқүжқүж ӘејҸдјҡзӨҫ
- гӮҝгғ«гӮ¬гӮ°гғ«гғјгғ—ж ӘејҸдјҡзӨҫ
- еӨ©ж–үгғӘгғҒгӮҰгғ ж ӘејҸдјҡзӨҫ
- иҙӣйӢ’гғӘгғҒгӮҰгғ гӮ°гғ«гғјгғ—ж ӘејҸдјҡзӨҫ
- гӮўгғ«гғҷгғһгғјгғ«дјҒжҘӯ
- гғқгӮ№гӮігғ•гғҘгғјгғҒгғЈгғјгӮЁгғ ж ӘејҸдјҡзӨҫ
- гғ¬гӮҫгғҠгғғгӮҜж ӘејҸдјҡзӨҫ
- гӮўгғігғ—гғӘгӮҰгӮ№гғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјгӮә
- гғҠгғҺгӮ°гғ©гғ•ж ӘејҸдјҡзӨҫ
- JSRж ӘејҸдјҡзӨҫ
| гӮҝгӮӨгғ—еҲҘ | гӮЁгғігғүгғҰгғјгӮ¶гғјеҲҘ | еӣҪеҲҘ | ||
|
|
|
|
|
Related Reports
- зЎ¬еҢ–жҺҘзқҖеүӨеёӮе ҙ вҖ“ дё–з•ҢгҒ®жҘӯз•ҢиҰҸжЁЎгҖҒгӮ·гӮ§гӮўгҖҒгғҲгғ¬гғігғүгҖҒж©ҹдјҡгҖҒдәҲжё¬гҖҒжЁ№и„ӮеҲҘпјҲгӮЁгғқгӮӯгӮ·г...
- гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒ®жҙ»жҖ§зӮӯеёӮе ҙпјҡгӮҝгӮӨгғ—еҲҘпјҲзІүжң«жҙ»жҖ§зӮӯпјҲPACпјүгҖҒзІ’зҠ¶жҙ»жҖ§зӮӯпјҲGACпјүгҖҒжҠјгҒ—еҮәгҒ—гҒҫ...
- гғҷгғҲгғҠгғ гҒ®гӮ№гғ—гғ¬гғјжҺҘзқҖеүӨеёӮе ҙгҖҒгӮҝгӮӨгғ—еҲҘпјҲжә¶еүӨгғҷгғјгӮ№гҖҒж°ҙжҖ§гҖҒгғӣгғғгғҲгғЎгғ«гғҲпјүгҖҒеҢ–еӯҰеҲҘ...
- гӮөгӮҰгӮёгӮўгғ©гғ“гӮўгҒ®гӮ№гғ—гғ¬гғјжҺҘзқҖеүӨеёӮе ҙпјҡеҢ–еӯҰеҲҘпјҲгӮЁгғқгӮӯгӮ·гҖҒгғқгғӘгӮҰгғ¬гӮҝгғігҖҒеҗҲжҲҗгӮҙгғ гҖҒй…ў...
- гӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ®жҺҘзқҖеүӨгҒҠгӮҲгҒігӮ·гғјгғ©гғігғҲеёӮе ҙ - жЁ№и„ӮгӮҝгӮӨгғ—еҲҘпјҲгғқгғӘгӮҰгғ¬гӮҝгғіжҺҘзқҖеүӨгҖҒгғ“...
- зұіеӣҪгҒ®гӮ№гғ—гғ¬гғјжҺҘзқҖеүӨеёӮе ҙ - еҢ–еӯҰеҲҘпјҲгӮЁгғқгӮӯгӮ·гҖҒгғқгғӘгӮҰгғ¬гӮҝгғігҖҒеҗҲжҲҗгӮҙгғ гҖҒй…ўй…ёгғ“гғӢгғ«гӮЁ...
Table of Content
To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )
List Tables Figures
To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy
